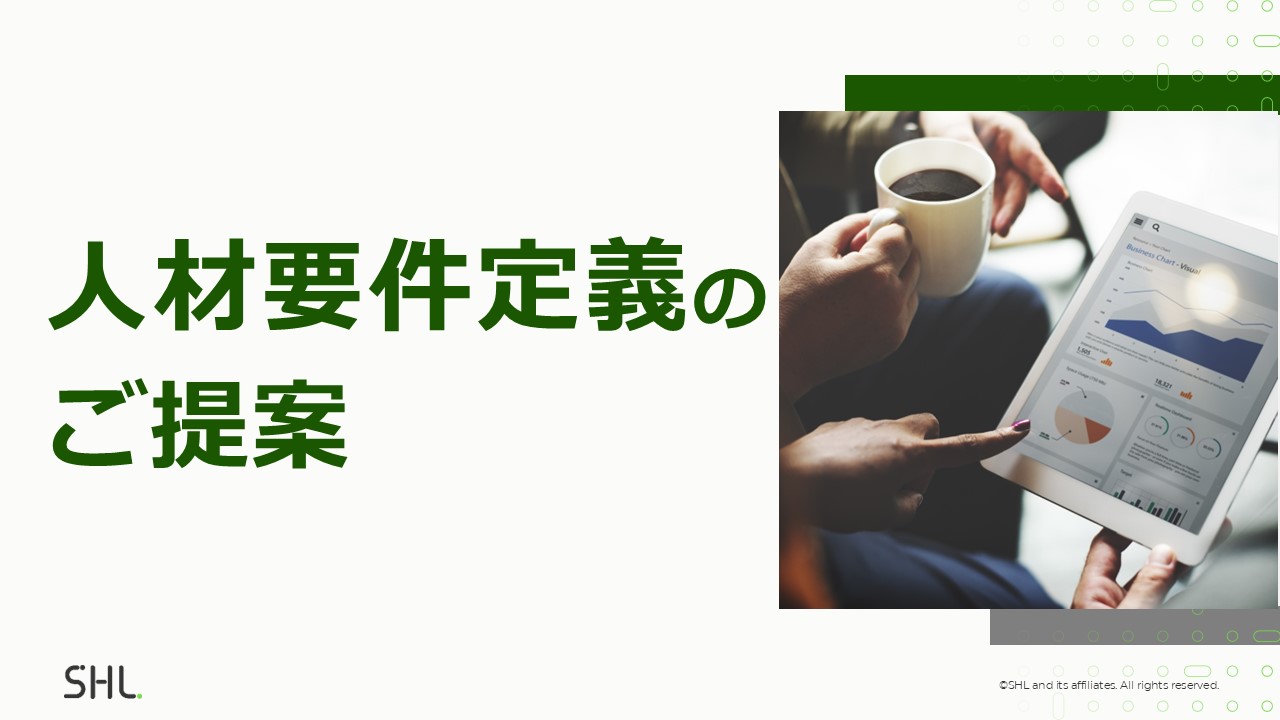0から始める採用基準設計~ファーストステップのすすめ~
目次をみる 目次を閉じる
新卒採用であっても中途採用であっても採用活動を行う際には採用基準として「求める人物像」を定義しておくことが重要です。選考時の評価だけでなく、母集団形成の方法にも影響を与える採用の指針といえます。
一方、企業の採用担当者からは、このような声がよく寄せられています。
・「求める人物像」が、いつどうやって作られたものなのか分からない。
・古すぎて今の会社とはマッチしない。
・定義があいまいで、評価者間、また選考プロセス間で、評価がぶれてしまう。
ビジネス環境の急激な変化から、こうした課題は年々増加しており、採用基準見直しのニーズは高まっています。
とはいえ、採用基準の設計は「優先度は高いが、具体的なやり方がわからず、手を付けられない」「現状でも運用できているから、今は直近の業務に手を回したい」といった感覚をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、パーソナリティ検査OPQを活用し、手軽に行える採用基準の見直し方法についてご紹介します。
高業績者に共通する特徴を明らかにする他、自社内で全体的に高い水準を示すコンピテンシーを確認することで、各職種や階層の職務適性だけでなく、組織風土に対する適性を判断する参考情報としても活用できます。
分析はExcelなどの表計算ソフトを用いる他、当社が提供している無料の分析ツールを使って簡単にOPQデータと評価の関係性を特定することもできます。分析の方法にご不明点がある場合は、ぜひ当社のコンサルタントにお尋ねください。
9枚のコンピテンシーカードを用いてディスカッションを行います。手順は以下の通りです。
1.9枚のカードにそれぞれ書かれた各コンピテンシーの定義を参照し、業務においてそれぞれどの程度必要かを検討します。
2.9つのうち、「必要ない」と思われるコンピテンシーを3枚捨て、6枚に絞ります。
3.残りの6枚を、「必要不可欠なもの」3枚、「あると望ましいもの」3枚に分けていきます。
このカードソートの過程でディスカッションを行い、判断の根拠を明確にしてゆきます。全員で同じツールを用いてディスカッションを行うことで、人材についての共通認識・共通言語を得やすくなり、堂々巡りや認識のずれを防ぐことができます。当社の専門家がファシリテーターを務めます。
重みづけやその理由を集計し、部署ごとに必要な適性を特定します。
「1.入社時データの分析」は定量手法と呼ばれ、データに基づいてこれまではどんな人材が活躍していたかを特定できます。「2.カードソート・ディスカッション」「3.アンケート」は定性手法と呼ばれ、これからどんな人材が必要になるかを検討できます。定量手法と定性手法を組み合わせることで、客観性と主観性、これまでとこれからの両方の要素を取り入れた採用基準を作ることができます。
現職者だけでなく管理職者の特徴の分析を行ったり、経営層に今後の経営方針も含めたインタビュー(ビジョナリー・インタビュー)を行ったりすることで、より長期的な視点で適切な採用基準を設計することもできます。
採用基準作成ファーストステップとして、本コラムがお役立ていただければ幸いです。
一方、企業の採用担当者からは、このような声がよく寄せられています。
・「求める人物像」が、いつどうやって作られたものなのか分からない。
・古すぎて今の会社とはマッチしない。
・定義があいまいで、評価者間、また選考プロセス間で、評価がぶれてしまう。
ビジネス環境の急激な変化から、こうした課題は年々増加しており、採用基準見直しのニーズは高まっています。
とはいえ、採用基準の設計は「優先度は高いが、具体的なやり方がわからず、手を付けられない」「現状でも運用できているから、今は直近の業務に手を回したい」といった感覚をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、パーソナリティ検査OPQを活用し、手軽に行える採用基準の見直し方法についてご紹介します。

1.入社時データの分析
採用選考でOPQを利用しているのであれば、そのデータを用いた分析が可能です。パフォーマンスを示すデータ(人事評価や営業成績など)とOPQデータを突き合せることで、職種や階層ごとにパフォーマンスに影響を与えるコンピテンシーを特定できます。高業績者に共通する特徴を明らかにする他、自社内で全体的に高い水準を示すコンピテンシーを確認することで、各職種や階層の職務適性だけでなく、組織風土に対する適性を判断する参考情報としても活用できます。
分析はExcelなどの表計算ソフトを用いる他、当社が提供している無料の分析ツールを使って簡単にOPQデータと評価の関係性を特定することもできます。分析の方法にご不明点がある場合は、ぜひ当社のコンサルタントにお尋ねください。
2.カードソート・ディスカッション
当社が実施する人材要件定義のためのインタビュー手法の一つです。現職者や管理者、人事部などを対象に、4~6名1グループでディスカッションをしていただきます。人材要件定義の対象となる部門の役職者が参加することが望ましいです。9枚のコンピテンシーカードを用いてディスカッションを行います。手順は以下の通りです。
1.9枚のカードにそれぞれ書かれた各コンピテンシーの定義を参照し、業務においてそれぞれどの程度必要かを検討します。
2.9つのうち、「必要ない」と思われるコンピテンシーを3枚捨て、6枚に絞ります。
3.残りの6枚を、「必要不可欠なもの」3枚、「あると望ましいもの」3枚に分けていきます。
このカードソートの過程でディスカッションを行い、判断の根拠を明確にしてゆきます。全員で同じツールを用いてディスカッションを行うことで、人材についての共通認識・共通言語を得やすくなり、堂々巡りや認識のずれを防ぐことができます。当社の専門家がファシリテーターを務めます。
3.アンケート
ボードメンバーや管理職者、現場のハイパフォーマーなどにアンケートを実施することによって、採用要件を定義することも可能です。 コンピテンシーの定義が書かれたアンケートを配布し、業務内容に照らして必要だと思われる順にコンピテンシーの重みづけを行っていただきます。重みづけやその理由を集計し、部署ごとに必要な適性を特定します。
「1.入社時データの分析」は定量手法と呼ばれ、データに基づいてこれまではどんな人材が活躍していたかを特定できます。「2.カードソート・ディスカッション」「3.アンケート」は定性手法と呼ばれ、これからどんな人材が必要になるかを検討できます。定量手法と定性手法を組み合わせることで、客観性と主観性、これまでとこれからの両方の要素を取り入れた採用基準を作ることができます。
現職者だけでなく管理職者の特徴の分析を行ったり、経営層に今後の経営方針も含めたインタビュー(ビジョナリー・インタビュー)を行ったりすることで、より長期的な視点で適切な採用基準を設計することもできます。
採用基準作成ファーストステップとして、本コラムがお役立ていただければ幸いです。

このコラムの担当者
霞 紫帆
日本エス・エイチ・エル株式会社